「EAP?エマージェンシーアクションプラン?緊急時対応計画ってなに?EAPってどうやって作ればいいの…」
「EAPを作成すれば安全配慮義務は果たされるの?」
緊急時に迅速かつ適切に救急対応をするためには、正しい知識とスキルを身につけ、AEDのような緊急時に必要な用具があれば大丈夫でしょうか?
EAP(エマージェンシーアクションプラン)とは?

EAPとは、Emergency Action Plan(エマージェンシーアクションプラン)という英語の頭文字をとったもので、日本語では、緊急時対応計画と呼ばれています。
救急対応には、「ヒト」と「モノ」が円滑に機能するための体制(救護体制)が必要です。
スポーツ現場で救護体制を構築する上で鍵を握っているのがEAP(エマージェンシーアクションプラン: 緊急時対応計画)で、安全配慮義務を果たす上では特に注目されています。
想定される緊急時にどのように対応するかを事前に計画し、初めて会場に来た人でも緊急時に遭遇した場合に迅速に対応できるように一目で分かりやすくまとまったシートです。

NPO法人スポーツセーフティージャパンの一員として、滋賀県スポーツ協会様と一緒に、EAPの作成手順のマニュアルを作成させていただきました。
下記のリンク先の滋賀県スポーツ協会様のホームページからEAP作成マニュアルとEAPのテンプレートをダウンロードできるのでぜひ参考にしてみてください。
公益財団法人 滋賀県スポーツ協会 EAP作成マニュアルについて 2024/12/17
EAPは1つ1つの緊急事態に対する手順を詳細に明文化されたマニュアルというのはよくある誤解です。
「突然心停止のためのEAP」「頭部外傷のためのEAP」「落雷事故のためのEAP」というものではありません。
突然心停止に特化したものはCardiac Emergency Response Plan (CERP)で、EAPとCERPをごちゃ混ぜになっている場合があります。
EAPはあくまでも、緊急事態と判断されてから必要な情報が記載されていて、緊急事態にEAPを見ながらでも適切に対応ができるようになるべく簡潔にまとめられていなければなりません。
突然心停止や頭部外傷など、1つ1つの緊急事態に対する手順に関しては、EAPではなく、「危機管理マニュアル」「安全マニュアル」などの中に記載します。
EAP作成時の注意点

EAPを作成する上で注意しなければならないのは、いつ、誰がこのEAPを参考にするかです。
施設側が利用者に向けて作成しているのであれば、緊急時に対応する施設側のスタッフの一人一人の連絡先を載せる必要はありません。
緊急時に利用者が施設側と連絡をとるときに必要な連絡先を載せるだけにします。
個人情報の開示には注意が必要です
また、平日と休日、祝日、時間帯によっては緊急時に搬送する最寄りの病院は異なる場合があるので、必要に応じてEAPを作成しなければなりません。
緊急時に搬送する最寄りの病院だけでなく、同じ会場だったとしても練習や試合、イベント、スポーツが異なる場合、同じチームだったとしても、現場にいるスタッフなどが異なる場合には必要に応じてEAPを作り直す必要があります。
EAPに記載する項目
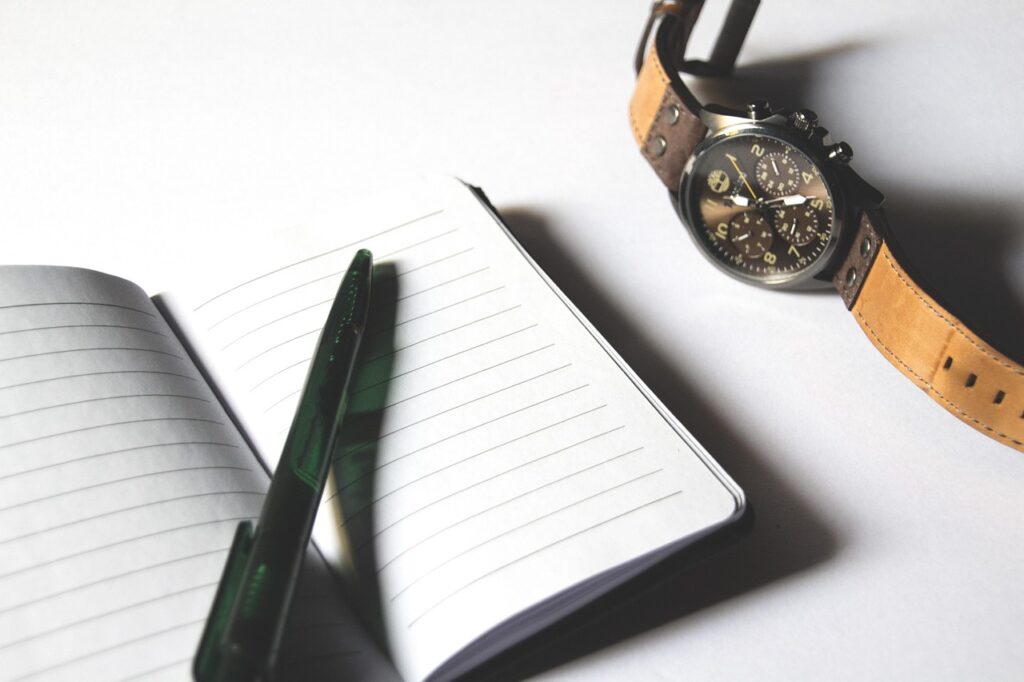
EAPには、下記の項目を記載することで、緊急と判断してからEAPを発動し、迅速かつ適切に医療従事者や救急隊員などの専門家へ引き渡し、または医療機関へ搬送することができます。
- 緊急時の責任者、連絡先
- AEDや担架などの救急器具や搬送器具などの設置場所
- 会場の住所と目印
- 最寄りの医療機関の情報
- 救急車の搬入経路が示されている会場の見取り図
他にも大会であれば、大会ドクターや看護師などのメディカルスタッフの待機場所や救護室の場所なども記載が必要です。
スポーツ現場でのEAPに基づく安全管理体制の構築方法

スポーツ現場でEAPに基づいた安全管理体制を構築するには少なくとも下記の6つのステップが必要です。

今回は6つのステップのうち、EAPを発動するような緊急時が起こる前の準備段階(ステップ1からステップ3)について解説します。
EAPの作成
EAPに基づくシミュレーション訓練の実施
当日のEAPハドルの実施
救急対応後のEAP発動報告書の作成
EAP発動報告書の分析
EAPと安全マニュアルの見直し・改善
1. EAPの作成
練習やトレーニング会場など自チームで実施するためのEAPは、当然、アスレティックトレーナやトレーニング指導者として作成する必要があります。EAPに記載する情報を入手したり、必要なモノを揃えたり、最寄りの病院などを含めた安全管理体制を整えます。
また、アウェーでの試合などでは、アウェーチームや大会運営者、施設管理者がEAPを作成してくれている場合には、自チームの情報を記載してEAPを完成させます。
同じ会場でも、練習や試合をする場合や、平日や休日などでは会場のレイアウトや最寄りの医療機関の情報が変わる場合があるため、その都度、このEAPを作成してください。
EAPを作成するのは、メディカルスタッフ、施設管理者や大会運営者、指導者になりますが、指導者のいないスポーツ現場では選手自らが作成する必要があります。
EAPはアスレティックトレーナーなどの専門家がいるから作成しなければならないというものではなく、すべてのスポーツ現場で作成する必要があるものと捉えることが重要です。

公益財団法人スポーツ安全協会様が運営しているスポあんラボでEAPの作成方法について解説させていただいています。
学校やスポーツでの突然死をゼロにするために取り組んでいる公益財団法人日本AED財団では、学校での突然死をゼロにするための様々な活動の一環として、学校やスポーツ現場でのEAPを作成し、ダウンロードできるようにテンプレートが用意され、スポーツ現場でのEAP作成ガイドラインをホームページで無料で提供されています。
ここからはEAPの作成方法について4つのステップで解説していきます。
EAPの作成ステップ① 必要な情報の収集
EAP作成の1つ目のステップは、EAPを作成するのに必要な情報の収集です。
誰がEAPを作成するのか、誰にEAPを共有するかによってEAPに記載する情報は若干異なります。
今回はEAPには絶対に必要な情報だけを紹介します。
119番通報時に必要な情報
緊急時と判断され、救急車を要請する際に119番通報中に伝える情報をまず収集します。
具体的には、
- 施設名/会場名
- 住所
- 目印
- 救急車/救急隊員のルート
「ヒト」緊急時に対応する施設側・会場側・イベント側のスタッフの連絡先・待機場所
緊急時と判断したときには、1人でやるのではなく、誰かに助けを求めることが大切です。
助けを求めるのは、救急隊員だけではありません。
スポーツ現場で緊急時と判断された際には、「手当」「調達」「連絡」「誘導」の役割をする人がいます。
大会やイベントでは、ドクターや看護師などの専門家がいる場合には、救急対応をなるべく早く引き継ぐことによってより適切な救急対応が期待できます。
また、救護室などの待機場所を把握する必要もあります。
緊急時に助けになるのは救護スタッフだけではありません。
施設側の運営スタッフや警備員などもスムーズにAEDなどを調達したり、救急車・救急隊員を誘導するには協力が必要です。
「モノ」AEDなど救急対応に必要な設備や備品の位置
最寄りのAEDがどこにあるのか、車椅子はどこに保管されているのか、水道や製氷機はどこにあるのか、など緊急時に必要な「モノ」の場所を確認するようにしてください。
EAPの作成時ではありませんが、当日、到着したときには運動やスポーツをする前に必ずAEDのアクセス・電源などを確認するようにしてください。
最寄りの病院・搬送方法
緊急時であれば、ほとんどの場合、救急車で病院へ搬送すると思いますが、自家用車などで病院へ搬送する場合があるので、最寄りの病院も必ず確認するようにしてください。
救急病院、整形外科、脳神経外科、眼科、耳鼻科、形成外科などスポーツによって起こりやすいケガに適切な病院・専門医の情報を収集してください。
EAPの作成ステップ② 緊急時アクションフローの作成
緊急時の救急対応に必要な「ヒト」と「モノ」の情報に加えて、119番通報と最寄りの病院などの救護体制に関する情報を収集した後は、実際に緊急時に誰がどのような役割を担うかの流れである緊急時アクションフローを作成します。
緊急時アクションフローでは、下記の3つのポイントが一目でわかるようにします。
- どのようにEAPを発動するかというEAPサイン
- EAPが発動されてから、誰がどのような役割を果たすのか
- どこに傷病者を搬送するのか
緊急時における救急対応の目標は、適切に手当をしながら、救急隊員などの専門家にいかに迅速に引き継ぎ、医療機関へ搬送することです。
EAPの作成ステップ③ 地図の作成
緊急時アクションフローを作成してから、ステップ①で収集した情報を元に、見取り図を作成していきます。
見取り図の中には、AEDなどの「モノ」や救護室だけではなく、階段や段差など搬送の障壁になるようなものもわかるようにします。
また、救急隊のルートも示すとわかりやすくなります。
EAPの作成ステップ④ 必要項目の記入
EAP作成の最後のステップとして、緊急時に必要な情報を必要項目に記入していきます。
緊急時に連絡する必要のあるスタッフやスタッフの連絡先、救急車を要請する際に伝える住所、最寄りの病院の情報などです。
地図の上にもAEDの場所などを示していますが、緊急時の際に地図上ではすぐに見つからない可能性もあるので、文字でも記載しておきます。
基本的には、EAPの作成は前日までに完成させ、当日の会場で確認するというステップです。
正直、残念ではありますが、まだまだ日本ではこのEAPは認知され始めてはいますが、普及されているとは言えない状況です。
ただ、安全配慮義務、法的リスクなどを考慮すると絶対になるのがEAPです。
事前に緊急時を想定して準備をしていたのかがとても重要になります。
訴訟が起こらなかったとしても、「事前に何かできたのではないか」と自問自答し、ご自身を責めることも考えられます。
「事前にできること」、それがEAPを作成し、適切に迅速に対応するための救護体制を構築するためのステップです。
もちろん、どのように緊急事態と判断するのか、胸骨圧迫やAEDの使い方などを学ことも必要です。
スポーツ現場で緊急時になった場合に、EAPがなければ、その場で必要な情報を収集することに時間がかかってしまい、迅速な対応ができなくなります。
緊急性が低いケガなどであれば、時間をかけても問題ありませんが、緊急時の場合には、対応する時間は一刻を争います。
2. EAPに基づくシミュレーション訓練の実施
スポーツ現場でのEAPを作成したら、緊急時にEAPが実際にスムーズに機能するかを検証するためにシミュレーション訓練を実施します。
シミュレーション訓練は、少なくとも年に1回実際に練習や試合、トレーニングをする会場で実施してください。
トリプルH(心停止や頭頚部外傷、労作性熱射病)などスポーツ現場で起こる緊急時を想定して、しっかりと知識とスキルを持っている人が、必要な救助器具や搬送器具を使用して適切に迅速に対応できる体制かを検証します。
迅速かつ適切に緊急時に対応できる体制が整っているかは、シミュレーション訓練中に時間を計測しながら検証する必要があります。
例えば、突然心停止の場合には、倒れてから緊急時と判断しEAPを発動してからAEDの1回目の電気ショックまでの時間を測定し、3分から5分以内に対応できているかが重要です。

突然心停止を想定したシミュレーション訓練で実際にチェックしている内容を下記の記事で解説しています。
ぜひ読んでみてください。
シミュレーション訓練では、実際の現場にいる人がなるべく全員参加する必要があるため、シミュレーション訓練で検証しているときにチェックする人は、実際の現場にいない人が担当します。
アメリカの大学では、アメリカンフットボールにはヘッドアスレティックトレーナーが担当し、アシスタントアスレティックトレーナーは基本的にはアメリカンフットボールの活動には関与しないので、アメリカンフットボールにおけるEAPのシミュレーション訓練では、アシスタントアスレティックトレーナーがチェック係を担当していました。
3. 当日のEAPハドルの実施
大会や試合などでは、このEAPを元に関係者が試合前に集まり、緊急時にどのように対応するかを話し合うミーティングを実施しています。
Bリーグでは、2024年のシーズンから試合の前に開催することを義務化されています。
この試合前に関係者が緊急時にどのように対応するかを話し合うミーティングのことを私が所属しているNPO法人スポーツセーフティージャパンでは分かりやすくするために、EAPハドルと呼んでいます。
試合前にどのタイミングで集まるかは、団体によって異なります。
私がアメリカのラスベガスで活動していた高校では試合の30分前に設定されていましたが、NFLではキックオフの60分前に設定されています。
また、試合前にいつ集まるかも微妙に違いますが、呼び方も多少の違いがあります。
アメリカのアスレティックトレーナーの団体であるNational Athletic Trainers` Association (NATA: 米国アスレティックトレーナーズ協会)では、メディカルタイムアウト/ EAPタイムアウトと呼んでいます。
また、日本では、日本ラクロス協会がSafety Time Outと呼んでいます。
このEAPハドルに参加する関係者は、団体などによって変わりますが、
- 両チームのメディカルスタッフまたはチームの責任者
- 試合の審判
- 大会の責任者
- 大会ドクター
- 試合会場の施設管理責任者
- 救急隊員
などが含まれます。
救急隊員については、日本の場合には市区町村など行政が主催者の場合には試合会場に待機する場合がありますが、ほとんどの試合や大会の会場には待機していない、または民間の救急車と救急隊が待機しているかと思います。
私が救護スタッフとして活動しているトレイルランの大会では市区町村が主催者もしくは地域振興のイベントの1つとして位置づけられているため、スタート地点またはゴール地点に待機してくれている体制を整えてくださっているので本当に助かります。
EAPハドルを実施する際に救急隊員がいない場合には、事前に消防署に行き、EAPについて説明しに挨拶に行くことが大切です。
EAPのまとめ
EAPとは、エマージェンシーアクションプランの略で緊急時対応計画のことを言います。
事前に試合や練習、トレーニングのときに緊急時になった場合に必要な情報を集めておき、どのように対応するかを分かりやすくまとめられた1枚の紙になります。
スポーツ現場で緊急時になった場合に、迅速に対応できるようにするために、アスレティックトレーナーは、しっかりとEAPを作成、または確認して、スポーツ現場にいる人たちとEAPに記載されている情報を共有する必要があります。
チームでは、メディカルスタッフだけではなく、選手やコーチングスタッフ、チームや試合の運営スタッフと一緒にEAPに基づくシミュレーション訓練を実施して、EAPを検証する必要があります。
試合や大会などでは、大会側や相手チームのメディカルスタッフや救急隊員などと緊急時に親密に連携できるように試合前にEAPハドルを開催して、顔合わせや最終確認をする必要があります。
EAPを作成したとしても、作成したEAPを共有しなければ意味がありませんし、練習や試合の当日には道路を工事しているかもしれません。
EAPを作成したら必ず、作成したEAPが本当に機能するのかを検証し、練習や試合の当日には最終確認するようにしてください。
特に、EAPについてはEAPを作成すればいいというものではなく、作成したEAPを基にチーム全体、または会場全体の緊急時における救急対応の体制を整えるために活用する必要があります。
スポーツ現場でのEAPに関する参考文献
- Scarneo-Miller SE, et al. National Athletic Trainers` Association Position Statement: Emergency Action Plan Development and Implementation in Sport. J Athl Train. 2024;59(6):570-583.
- Andersen J, Courson RW, Kleiner DM, McLoda TA. National Athletic Trainers’ Association position statement: emergency planning in athletics. J Athl Train. 2002;37(1):99–104







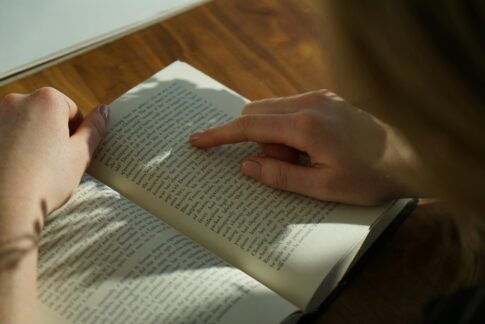








今回の記事では、「EAPを活用してスポーツ現場でどのように安全管理体制を構築していくか」について解説します。